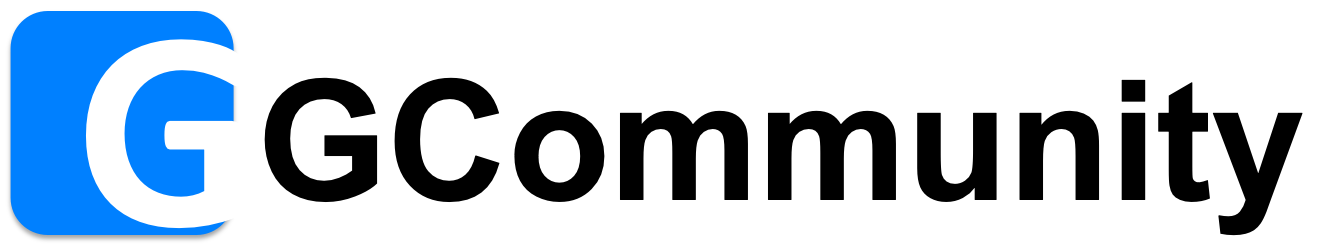患者体験談

こんにちは、がーすけと申します。
若い世代での発症が多いIBDですが、私は30代での発症でした。なので、限られたお話しかできませんが、自炊は結構こなしている方なのでその辺で何かお役に立てたら嬉しいなと思っています。
Twitterの方にもノンフライ調理や低脂質の食事を投稿しているので、良かったらお気軽にお声掛けください。(便乗宣伝)
ユーザー名→ @gask_UC アカウント名→がーすけUC@暇人。
治療経過の説明がだいぶ複雑で長くなってしまったのですが、サラッとお付き合いくださると嬉しいです。
ーー発症から診断まで
買い物に行く前にトイレを済ませようと便座に腰掛けると、何の兆候もなくお尻からガスと一緒に血が噴き出しました。はじめは痛みもなく痔かと思いましたが、その後尋常じゃない量の血液が便に付くようになりました。その時はまだお腹も緩くないし腹痛もありませんでした。
1ヶ月ほど様子を見ていたら、徐々に便が緩くなり腹痛や急な便意も増えたので消化器内科クリニックを受診しました。クリニックでは問診から痔と過敏性腸症候群の併発であろうと診断され、イリボーを処方されました。しかしその後1日ごとに症状が悪化。
堪えきれなくなり再度クリニック駆け込んだところ緊急で大腸カメラの実施となり、潰瘍性大腸炎(左側大腸炎型・中等症)の診断を受けました。診断を受けたときは下痢と腹痛を止めて欲しいとずっと思っていたので、やっと診断を受けて効果が望める薬を出してもらえるという安堵感がありました。
ーー治療経緯
はじめはメサラジン腸溶錠(アサコールのジェネリック)とペンタサ注腸を処方されましたが、その後も便回数がどんどん増えたため3日後からプレドニンを追加してもらいました。そのおかげで便回数が顕著に減りましたが、高頻度でメサラジンが溶けずに出て来ている事に気付き、先生の判断でアサコールに変更してもらいました。
その甲斐もあってか一旦は寛解状態になりました。しかし、減薬後すぐに出血し始めたため投薬量を戻し、飲み薬もアサコールからリアルダに変更となりました。しばらく小康状態でしたが再び出血が始まり、そこからは悪化の一途を辿りました。
レクタブルも追加されましたが多少便回数が減っただけで腹痛にはあまり効果がなく、家ではほとんど横たわっている状態でした。家事をしていても洗濯物を運んでくるとフラフラで15分ほど横になって腹痛の波が去るのをひたすら待つ。また5分ほど干すと次の腹痛の波がくるのでまた15分ほど横たわって治まるのを待つ。そのような状態が1ヶ月続きました。
その後再び便回数が増えた為プレドニン20mgを開始。それでも症状は改善せず、大腸カメラで左側大腸炎型・重症との診断をされクリニックから市立病院のIBDの専門医を紹介されました。この時発症から1年3ヶ月くらい経っていました。
市立病院ではプレドニン20mgを継続しながら血球成分除去療法(L-CAP)を行い、大半の症状が消失しました。そしてプレドニンをゆっくり減らしていきゼロにできました。(レクタブルは減量して継続)
時々、微量の出血がありつつもそれなりに落ち着いた症状で過ごせましたが、3ヶ月後に再燃し、ロイケリンの追加と併せて2度目のL−CAPを行いました。しかし2度目のL−CAPは充分な効果が得られずエンタイビオを開始しました。いくつもあるバイオ製材の中でエンタイビオを第1選択とした理由は家族に結核性抗酸菌症(肺MAC症)の既往があったためです(人への感染はしない)。
エンタイビオの効果がしっかり出るまでしばらく掛かると言われ、その時点で症状が辛かったのでゼンタコートを処方してもらいました。本来はUCの場合プレドニンが選択されるそうですが、1回目の投与時に様々な離脱症状に悩まされた為、主治医が考慮してくださいました。
エンタイビオの投与後、徐々にゼンタコートを減量してもらいました。その後しばらくロイケリン、エンタイビオ、リアルダ、ペンタサ注腸を行ってきましたが、インフルエンザに感染した事をきっかけに骨髄抑制を起こした為、ロイケリンの投与を中断する事になりました。その後、直腸を中心に再燃しましたがエンタイビオの投与のタイミングと重なり、3ヶ月ほどで落ち着いて現在に至ります。
発病から4年弱と比較的病歴が短いにも関わらず寛解と再燃を繰り返していますが、その度に私の体質や考え方、不安に思う事を取り入れながら個人に合わせた治療を適切に選択してくださる今の主治医をとても信頼しています。
ーー診断後にされた食事のアドバイス
診断直後はご飯を食べる意欲はありませんでしたが、症状の軽減とともに食欲も徐々に出てきました。友人に病気のことを伝えたら本を買ってきてくれたこともあり、その後自分でも2-3冊買って少しずつ勉強していきました。
はじめのクリニックでは主治医から「牛乳は飲まない方が良い」「豆乳はやめた方が良い」など避けた方が良い食材が徐々に追加されていきました。しかし、それらを摂取しても症状が出なかった事から闇雲に制限させられている感が拭えませんでした。
早速何を食べたら良いのか分からなくなり、食事はロシアンルーレットのような感覚になりました。診断後半年から1年位は鮭とはんぺんと鶏胸肉を毎日ローテーションして食べるような生活でした。
転機が訪れたのは先述の市立病院に転院した時です。現在の主治医に「食べちゃいけないものはありますか?」と聞いたら「少しならいいんじゃない。何でも食べて良いよ。一般論より自分にとって合うか合わないかの方が遥かに大事だよ。」と言われました。
この言葉で私の怯えと理不尽な感情は取り除かれ、救われた思いになりました。そこからトライアンドエラーを重ねて少しずつ自分が食べられる食材の幅を増やしています。
ーー体調に合わせたレシピ作り(食べたい物を食べられるように)
元々自炊するタイプで自己流レシピを作っていたので、そこに自分の体調に合うよう工夫を加えていきました。
手に入りやすい食材を選び、多少体調が悪くても作れるよう簡便さも意識しています。硬いものがお腹に合わないので別の食材で代用したり皮を剥いたり、繊維は細かく刻んで蒸し焼きにする等しています。口の中で何度も噛まなくても良いよいような柔らかさを意識しています。
また、物足りなくならない様に”風味”をつける工夫もしています。例えばバター風味が欲しい時はバターミルクパウダーを使います。脂質は低いですし香りとコクが出る気がします。
自分に合う調味料も積極的に探しています。例えば麻婆豆腐を食べたくなった時は、既製品の食品ラベルで原材料を確認します。そこに甜麺醤やXO醤と書いてあったら、それらの調味料に刺激物(唐辛子など)が入っていないのを確認して揃え、麻婆豆腐を作ります。
揚げ物もすぐには怖くて試せなかったのですが、どうしても食べたくなりノンフライで作るようになりました。
カレーもはじめは恐れていましたが、「バーモントカレーの赤ちゃん用」のルーから始めて自分に合うルーを探しました。「カレーの王子様」では出血しましたが、バーモントは最終的にOKで現在は低脂質のバーモント(甘口)を使用しています。
ハヤシライスについては、ルーは脂質が低い商品を選んでもお腹が緩くなりました。そこでハヤシライスの原材料を調べ、現在は1回使い切りのONEのフォンド・ヴォー、ケチャップ、トマトジュース、脂の少ない赤身部分の牛肉を使ってハヤシライスを作っています。
大丈夫な調味料を組み合わせて味付けのレパートリーも徐々に増やしました。ケチャップとソースがOKならBBQソースも大丈夫だろうと試したり、低脂質マヨネーズもちょっと怖かったので、無脂肪ヨーグルトと半々にしてポテサラなどに使うといった具合です。
私の場合は、料理を作ることよりも食べることが好きです。好きなものを食べる時にお腹のことで苦しまないために、後々楽をするために料理に関して研究したり色々な工夫をしています。
食事に対する恐怖心が薄れるまで半年ほど掛かりましたが、今はどのくらいが許容内かをある程度予想できるようになりました。もちろん体調によっては何を食べてもダメな時もあります。
診断されてすぐは不安ばかりだと思いますが、食事を怖い時間のままにして欲しくないなと思います。診断直後、IBDのレシピ本を送ってくれた友達に「もう食べる楽しみは捨てた」と言ったら「これからは食べられる事への喜びだね」と言い換えてくれました。今も心に残っている言葉です。
ーー主人のサポートと生活で意識していること(疲れは大敵)
主人には病気のことは自分で説明しました。なので、おおよそどういう病気なのか文献を読んだ程度には理解してくれていました。しかし、重症化して市立病院に転院する時に私の大腸カメラの画像を初めて一緒に見てもらったところ、それまでとは違った意味で症状の重さや辛さを理解してくれたようでした。
私はこれまでの経験から疲労が続くと再燃に繋がるように感じています。「ちょっと疲れたな、でももう一踏ん張り」が禁物です。なるべく疲れさせない、疲れたら予定を放り投げて休むようにしています。そうしないとより長期間休むハメになりますので、少々もどかしいですがこれが最善と思っています。(トイレで出血と出くわすところを想像して我慢です。)
主人にもこの話はしていて、夜は疲れるので家事や洗い物を時々手伝ってもらうようにしています。夕食も頑張って作らないようにすることを理解してもらっています。患者として、自分の状況を自分で説明してわかってもらうことは大切ですし、家族の理解と協力は本当に不可欠だと思います。
ーー他の患者さんへのメッセージ
人間には波があるので、どれだけ穏やかに保とうとしても卑屈になる時があると思います。良い歳をした大人ですら卑屈になることもあれば、やさぐれる時もあります。「みんないいよね、なんでも食べられて…」みたいな(笑)。
よく折れない心という言葉を耳にしますが、私は折れっちゃってもいいんじゃないかという考え方でいます。折れて休んで、いつか立ち直れば結果オーライです。
話が逸れましたが、そういったマイナス感情はみんな持っているので、マイナスな感情であっても患者同士なら分かり合えることがあると思います。
痛みの共有というのは思っている以上に大きな癒しになります。難病と知って塞ぎ込んだり、病気になった自分を受け止められないこともあると思いますが、仲間とは思わなくてもいいので一人で抱え込まずに同じ心の痛みを分かってくれる人との繫がりをぜひ持って欲しいと思います。