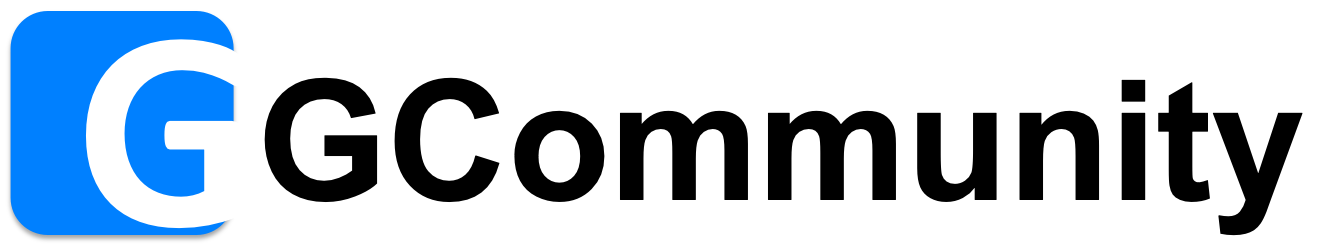質問&おしゃべり
8/29(日)に開催された28名が参加したZoomミニレクチャーレポートの第二弾です。今回は治験部分について紹介します!
アメリカの医療制度と患者さんの特徴
まず初めにアメリカと日本の治験への取り組みの違いを知る上で重要なアメリカ医療制度とアメリカの患者さんの特徴を紹介しました。
<医療制度の特徴>
• 医療費が非常に高い。
• 公的保険、民間保険、無保険などに分かれ、収入によって加入できる保険や受けられる治療が大きく異なる。
<患者さんの特徴(宮﨑主観)>
• 自分で治療を選択する、自分にとって価値のある、意味のある治療を主体的に選択しようとする患者さんが多い印象。勉強熱心で多くの情報を集めている印象。
• 治療の費用(自己負担額)がどの程度かかるのかが大きな関心事。
このような背景を踏まえ、アメリカでは、無償(もしくは協力費を得る形)で新しい治療を試せる臨床研究や治験に対し、特に所得レベルが比較的低い方を中心に多くの患者さんが興味を持っています。
アメリカの治験紹介サイト
アメリカでは臨床試験・治験を紹介するサイトなどが充実しています。以下の例は僕が所属していたミシガン大学の臨床試験・治験紹介サイトです。

このサイトでは、患者さんがサイトに登録して自分が該当する研究を探すことができます。さらにサイトを通じて治験コーディネーターが該当する患者さんを探し、直接お声がけできることも可能な仕組みとなっています。
Gコミュニティの治験に関する取り組み
次にGコミュニティの取り組みとして、治験に関する情報や治験参加体験談などが掲載されているページを紹介しました。現在クローン病患者さんを対象とした治験が2本紹介されていることに加え、体験談や患者さんからの治験の質問に答えた記事についてもまとめています。
https://gcareglobal.com/clinicaltrial-2/

その後、事前にいただいていた治験に関する質問にお答えしました。
治験の一般的なメリット・デメリットは?
<メリット>
• まだ通常はアクセスすることのできない、比較的効果と安全性が検証されている画期的な治療薬を試すことができる。
• 専門性の高い医師・試験コーディネーターのサポートのもと、治療を受けることができる。
• 負担軽減費等のサポートを受けられることが多い。
<デメリット>
• 通院頻度が高くなる可能性がある。
• 一時的に転院しなければならないこともある。
• プラセボに当たる可能性がある。(ただし効果がない場合は参加中断も可能)
患者さん個々人でメリット・デメリットがあり、どの試験を選択するかで異なる可能性もあるので、治験コーディネーターと話しながら疑問を一つずつ解消することが大切です。治験コーディネーターとはウェブスクリーニングの後比較的容易にお話しすることが可能であることが多いです。
日本において治験情報がまとまっているウェブサイトは?
UMIN(臨床試験登録システム)に日本で行われている大半の治験が掲載されています。以下のウェブサイトの「対象疾患名」に潰瘍性大腸炎やクローン病と入力して検索ボタンを押すと関連研究が一覧で表示されます。
https://upload.umin.ac.jp/cgi-open-bin/ctr/index.cgi?function=02
治験期間終了後に服用を一度停止することで承認後に同じ薬剤を使えなくなるリスクは?(当日お答えできなかった質問)
治験薬を使った後に一度期間を置いてしまうとその治験薬が承認された後に使いにくくなる可能性は否定できないと言われています。
一方で、治験薬を長期に渡って使用し、効果と安全性を確認する長期投与試験が付随している治験も多いです。例えば、Gコミュニティで紹介している治験においても、条件に該当し、患者さんが望むのであれば、長期試験への継続参加が可能となっています。
興味を持った治験があった場合に治験の期間がどのくらいなのか、長期試験を行っているのかについても治験コーディネーターや担当の医師に相談されることをお勧めします。
治験の具体的なプロセスについて
治験が実際にどのように行われるかについては患者さんの置かれている状況によって異なります。もし現在通院している施設で治験が行われている場合は転院などの必要なく治験を受けることができます。
一方現在通院している施設で治験が行われていない場合は、主治医と相談し、紹介状を書いてもらって治験が行われている施設に転院する必要があります。
その後の流れについては過去に参加経験のある患者さんの体験談に詳細が記載されていますのでぜひ参考にしていただけましたらと思います。
https://gcarecommunity.com/article/599
次回はZoomミニレクチャーの食事・栄養パートについて紹介予定ですのでぜひお楽しみに!
コメント一覧
コメントはありません。